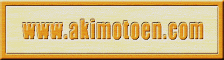
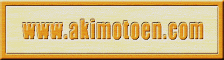
茶・関連用語
| 用 語 | ふりがな | 内 容 |
| 朝 露 | あさつゆ | 茶の品種:茶農林2号(登録番号) |
| 荒 茶 | あらちゃ | 摘んだ茶葉を蒸して、揉んで、乾燥させ、 飲用とする為の基本的な加工をした状態。 通常、不揃いで、含有水分が多い。 その為、この後で細かいところを除いたり(粉茶・芽茶)、 茎が混入していれば取り除き(茎茶)、 含有水分を減らすと同時に、香気を増すために、 仕上げの火入れをします。 |
| カテキン | かてきん | 茶に含まれるタンニン物質で、渋み成分。 殺菌、坑ウィルス活性、 坑酸化作用を持つポリフェノールの仲間。 過剰になると動脈硬化、脳梗塞、 糖尿病、ガンなどに、なりやすいと言われている 活性酸素を抑える作用を持っています。 |
| カフェイン | かふぇいん | 茶素。茶葉に含まれるアルカロイド(アルカリ性を示す、 窒素を含む塩基性の有機化合物。) 興奮、利尿作用があります。 |
| 釜炒り茶 | かまいりちゃ | 茶葉の酸化酵素の働きを止めるために、 熱を加えますが、この場合蒸気ではなく、 鉄釜に茶葉を入れ、直接的に加熱する方法。 この釜炒り製法を、中国式と呼びます、 蒸気で熱を加える蒸し製法を、日本式と呼びます。 |
| 玉 露 | ぎょくろ | 新芽が成長を始めた頃より、茶園に、よしず、 藁(わら)などで、覆いをかけて、直射日光を当てない ようにすると、あま味、うまみ成分である テアニンなどの、アミノ酸が増えます、 反面、渋み成分であるカテキン類は、 抑えられ増えません。 よって、ふくよかな甘味のあるお茶になります。 新芽の成長に合わせて、段階的に20日間以上 覆いをかけ、最終的には、ほとんど完全に 近い状態まで、日光を遮断した状態の茶園から、 摘まれ製造されたものを、玉露と呼びます。 香りに関しては、覆いをかけたことによる、 独特な香りがあります。 この香りは、お茶を摘む1週間前頃から、 簡易的に覆いをかけた茶園から摘まれ、 製造されたお茶(かぶせ茶)にも、この独特な香りはあり、 この香りを、覆い香(おおいか)と、言います。 お茶の入れ方は、特にお湯の温度に注意して、 50度位のお湯で、2分くらい待って、時間をかけて ゆっくりと、いれて下さい。 |
| 茎 茶 | くきちゃ | 荒茶を精製する段階で選別され、出たものです。 青々とした、さわやかな香りがあります。 |
| 玉緑茶 (グリ茶) |
ぎょくりょくちゃ ・ぐりちゃ |
釜炒り製と、蒸し製の2種類があります。 製造の時に、通常行われる、最終に茶の形状を 整える作業をしていない為に、伸びた形にならず、 外観が丸くなり、その丸い感じからグリ茶と呼ばれます。 また、玉緑茶とも呼ばれます。 |
| 玄米茶 | げんまいちゃ | 煎茶、番茶に炒った玄米を加えたもの。 香ばしい風味を持つお茶です。 |
| 粉 茶 | こなちゃ | 荒茶を精製する段階で、ふるいにより細かい部分が 選別され出たものです。 いれ方は、熱いお湯でさっと入れてください。 はじめに急須に粉茶を入れる時に、ついつい多量に 入れ過ぎてしまう事がありますので、お気をつけ下さい。 |
| 煎 茶 | せんちゃ | 基本的には、茶葉を、蒸して、揉んで、 乾燥した緑茶で、玉緑茶(グリ茶)と違い、 丸くなく伸びた形状をもつものです。 他に、番茶との区別として、茶の仕上げ工程中に、 その品質から上級茶(煎茶)・下級茶(番茶)と、 分けられたり、茶葉を摘む時期から、 区別して呼ばれたり、します。 煎茶と番茶の区別方法は、 その着目点により、いくつかの方法があります。 |
| だん茶 | だんちゃ | 茶葉を蒸して、柔らかくした後に、型に入れ圧縮して、 塊(かたまり)・板状などにしたものを、乾燥させて作ります。 緑茶から作ったものを、緑だん茶。 紅茶から作ったものを、紅だん茶。と、言います。 |
| タンニン | たんにん | 渋み成分、茶のタンニンは、カテキンが主体。 坑酸化作用を持つ。 |
| 茶 | ちゃ | ツバキ科に属する、常緑の潅木。 潅木(かんぼく:背丈の低い樹木) |
| テアニン | てあにん | 旨(うま)味・あま味、成分。 |
| 碾 茶 | てんちゃ | 玉露と同じように、覆いをかけた茶園で成育し、 摘んだ葉を蒸した後、揉まずに乾燥させたもの。 この碾茶(てんちゃ)を、石臼(いしうす)で、 挽いたものが、抹茶。 |
| 凍霜害 | とうそうがい | 新茶時期に、晴天無風の明け方に、気温が 急激に下がることにより、霜が降りたり、 茶芽が凍結して、新芽が茶色に変色したり、 枯れた状態になること。 茶園の中に扇風機のような、防霜ファンを設置して、 冷気の流れを、変えるようにします。 |
| 番 茶 | ばんちゃ | 茶葉が、伸びて大きく、硬くなったものを原料として、 作られたお茶。 4月〜5月(春)に、その年最初に摘まれた、 茶葉から製造されたお茶、1番茶・一茶(いっちゃ)を煎茶。 その後に芽が伸びて、(夏)の頃に、その年・2番(回)目に摘まれた、 茶葉から製造された二茶(にちゃ)以降のお茶を、 番茶と、呼ばれてもいます。 茶としては、下級に属します、夏の強い光を受けた為に、 味は、渋みが強くなります。 その反面、その渋み成分であるカテキン類が、 煎茶より多くあるので、注目されています。 煎茶の項でも記述致しましたが、煎茶と、番茶の区別方法は、 その着目点により、いくつかの方法があります。 |
| 八十八夜 | はちじゅう はちや |
立春から数えて、88日目の日。 5月2日頃で、閏年(うるうどし)には5月1日、 新茶の開始時期になります。 |
| 焙 茶 | ほうじちゃ | 番茶・煎茶を、焙じて製造したものです。 水色は、明るい茶色で、香ばしい、 さっぱりとした風味を持っています。 焙じる(火であぶる、焙煎)作業により、 作業前のお茶とは、かなり大きな成分変化をします。 カフェインが減少し、夜寝る前や、 病院等でも使われています。 茎茶を焙じた、茎ほうじ茶もあります。 通常のほうじ茶は、熱いお湯で、さっといれますが、 茎ほうじ茶の場合には、同じく熱いお湯を使いますが、 すこし時間をかけて、ゆっくりと入れてください。 地域により、ほうじ茶の事を、お番茶と呼ぶところもあります。 |
| 抹 茶 | まっちゃ | 碾茶(てんちゃ)を、1分回・約60回転する 石臼(いしうす)で、挽いて、微粉状にしたものです。 |
| ミル芽 | みるめ | 明るい緑色で、若く、柔らかい新芽。 |
| 芽 茶 | めちゃ | 荒茶を精製する段階で、ふるいにより細かい部分が、 選別され出た物の中で、 粉茶と、更に選別された、茶の芽先部分。 |
| 銘 茶 | めいちゃ | 特別の名のある、良いお茶。 |
| やぶ北 | やぶきた | 茶の品種:茶農林6号(登録番号) 静岡県・杉山 彦三郎が、在来茶園から抜粋。 茶登録品種は、(平成16年)現在52種類ありますが、 品種的に優秀であり、地域の適応性が大き等により、 やぶきた種の普及率は、品種茶園の80パーセントを超える、 日本茶の代表品種です。 |