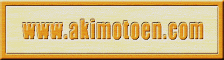
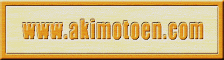
 茶葉の発酵と、分類。
茶葉の発酵と、分類。
| 発酵とは: | 簡単に申し上げますと、茶葉にある酸化酵素が、時間と共に、 活性化(働き始め)、茶の葉が赤く変色し、香・味が変化して行きます。 |
| 発酵を止める方法 | 茶葉に熱を加えることにより、この働きを止めることが出来ます |
| 発酵させてないお茶 | 緑茶 |
| 半発酵させたお茶 | ウーロン茶 |
| 発酵させたお茶 | 紅茶 |
茶葉を摘んだ後、短時間のうちに蒸気を当てて、
熱を与え発酵させない茶葉で作られたお茶は、
赤くならず、緑を保つので、緑茶と呼ばれます。
(追加事項)
お茶の製造過程の、蒸気を当て、蒸す作業方法の違いにより、
出来上がったお茶に、大きな特徴(違い)が現れます。
| ・深蒸し茶(ふかむしちゃ) ・特蒸し茶(とくむしちゃ) |
蒸す時に、通常の2倍以上の長い時間蒸して、製造されたお茶。 深=(通常より)物事の程度が大きい。度合いが強い。 特=(通常より)とりわけ。特別に。 深蒸し茶・特蒸し茶は、総称した呼び名であり、蒸しの程度の順を、示すものではありません。 |
| 特徴 | 形状 | 入れたお茶の濃度 | 味 | 香 |
| 細かい | 濃 | マイルド | 弱 |
形状に関しては、この、蒸気を当てる時間を長くすると、
茶葉がもろくなり、この後の製造工程中に、
茶葉の外周部が壊れて、細かく、粉の多いお茶になります。
その反面、差しが効く(急須でお茶を入れた時の抽出液は濃く、何回も、よく出る。)お茶になります。
味的には苦味が少なく、マイルドになります。
香りに関しては、青々とした香りが弱くなり、より蒸し量を多くすると、
香りそのものが、ほとんど無くなりますので、注意が必要です。
水色ばかりで(濃く出るが)、
香りのないお茶が、出来上がってしまいます。
その為、仕上げ乾燥の時に、必要以上に火を強くして、
火の香り(ほうじ茶のような香り)を、感じるように仕上げる方法が、
とられている場合もあります。
もし、お茶の中に茎があり、その茎が膨張した状態なら火の入れすぎで、
俗に言う、やけどしたと、言われる状態です。
お茶の蒸し方、最終仕上げの火の入れ加減は、
お茶の個性を決める、大きな要因となります。